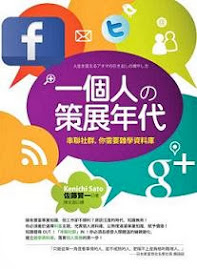「できませんと云うな」、これが口癖であったという立石一真。研究開発系企業として有名なオムロンの創業経営者です。
そしてオムロンは京都の会社。京都の研究開発系企業としては京セラが有名ですが、京セラの創業者・稲盛和夫が鹿児島出身であることは意外と知られていないようです。
オムロン(旧 立石電機製造所)の立石一真もまた、本書によれば熊本出身の九州男児でした。1900年(明治33)年に熊本に生まれ、1991年(平成3年)に没するまで、一貫して技術者として不可能へ挑戦し続けた熱い人だったのです。
縁あって京都で起業して、世界企業になった京セラとオムロン。稲盛さんにくらべて知名度では落ちるが、研究開発系企業としてのオムロンとその創業者・立石一真は、もっと知られていいのではないでしょうか?
立石一真自身が目立つことを嫌ったこともあって、すばらしい業績を残しているの対して立石一真その人については広く知られているわけではないようです。本書を読むまで、わたし自身、オムロンという会社については知っていても、立石一真についてはよく知らなかったわたしは、その感をつよくしました。
1960年に世界に先駆けて開発に成功した「無接点近接スイッチ」は、自販機、電話交換機、新幹線や自動車のメーター、工作機械などさまざまな分野で現在では当たり前のように使われています。
技術によって社会を変革するという創業者のつよい思いが反映した企業姿勢、これが端的に実現されたのが、世界初のオンラインCD(=現金自動支払機)やATMの開発でしょう。これによって、窓口業務が機械化されて金融機関の週休2日制が実現したことは、わたし自身が金融機関の関連企業にいたこともあり、たいへんありがたく思っています。
また、NHK『プロジェクトX』で紹介された自動改札機の開発ストーリーは、創業者・立石一真自身が主人公ではなく、開発にあたったエンジニアが主人公でしたが、技術によって社会を変革するという姿勢がすみずみまで浸透していることが、よく感じられるものでした。
イノベーションを軸にしたあるべき経営とは何か?
技術によって社会を変革するといういうことはどういうことか?
いち早く障害者の雇用をする企業を利益のでる営利企業として軌道にのせるなど、さまざまな領域でイノベーションを実現し、社会を変革していったオムロンと創業者・立石一真。ドラッカーとは公私にわたって親交がありました。
もっと知られるべき理想の経営者として、ぜひみなさまにも知っていただきたいと思い、紹介させていただいた次第です。
目 次
まえがき-ドラッカーが絶賛した日本人経営者
第1章 青雲の志
第2章 立石電機創業
第3章 倒産の危機、オートメーションとの出会い
第4章 プロデューサー・システム
第5章 夢のスイッチ
第6章 生い立ちと社憲
第7章 自動券売機、再婚
第8章 交通管制システム
第9章 CDと無人駅システム
第10章 健康工学、オムロン太陽電機
第11章 電卓の誤算
第12章 大企業病退治
最終章 人を幸せにする人が幸せになる
文庫版あとがき
立石一真 年譜
参考文献
湯谷昇羊(ゆたに・しょうよう)
1952(昭和27)年、鳥取県生れ。法政大学経済学部卒。1986年ダイヤモンド社へ入社し、以後、銀行を中心とした金融界を主な取材対象として活動。「週刊ダイヤモンド」編集長、同社取締役を経て、2008(平成20)年に退社し、フリーの経済ジャーナリストになる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。
<関連サイト>
「私の履歴書 立石一真 復刻版」 (日経Bizアカデミー 2013年10月3日)
・・日本経済新聞の名物連載「私の履歴書」がネットで読める
<ブログ内関連記事>
書評 『京都の企業はなぜ独創的で業績がいいのか』(堀場 厚、講談社、2011)-堀場製作所の社長が語る「京都企業」の秘密
『週刊ダイヤモンド』の「特集 稲盛経営解剖」(2013年6月22日号)-これは要保存版の濃い内容の特集
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート
ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end