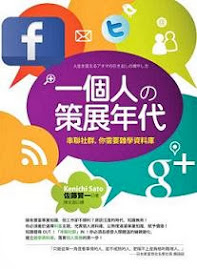このたび『国際人的資源管理』(関口倫紀・竹内規彦・井口知栄=編著、中央経済社、2016)がようやく出版、編著者の一人である関口倫紀(大阪大学経済学部教授)より、献本いただきました。
中央経済社による「ベーシック+」シリーズの一冊で、基本的に大学学部の学生向けテキストです。献本いただいたのは、わたくし自身は執筆はしておりませんが、全体の構成や推敲等で、全面的に関与しているためです。(・・この件については「謝辞」を参照)。ちなみに、編著者の筆頭に名前があがっている関口教授は、わたくしの元部下の一人で、超優秀(!)な研究者です。
帯に記されているように、「グローバル人材のHRMを初めて体系化」したもので、「国際的な人材配置、育成、報酬、評価、労使関係、海外派遣者マネジメントなどを体系的に解説」したものです。HRMとは、Human Resource Management の略で、日本語でいえば人的資源管理、ひらたくいえば人事管理と労務管理をあわせたものと考えればいいでしょう。
内容的には大学研究者が執筆した学部学生向けテキストなので、ビジネスパーソン一般や実務家の観点からみたら違和感がなくもないと思いますが、「日本では初の体系化」であるので、そこは目はつむることにしましょう。実務者向けの実務書とは、ちょっと違った色合いの本があってもいかな、と。
「グローバル人材」というものは、コトバが流通している割には、中身の議論があまりなされていないだけでなく、使う人によって定義もまちまちですが、本書をキッカケに、いろいろ議論が活溌になればいいかな、と思います。ビジネスの現場に即していえば、国境が存在する以上、国際人材の管理となることは当然といえば当然です。
「目次」を紹介しておきましょう。目次でザックリと感じをつかんでみてください。体系化の一例となるでしょう。
はじめに
第1部 基本フレームワーク
第1章 国際人的資源管理とは何か
第2章 グローバル化と多国籍企業
第3章 人的資源管理のフレームワーク
第4章 国際人的資源管理のフレームワーク
第5章 人的資源管理の地域別特徴
第2部 国際人的資源管理のサブシステム
第6章 国際人材配置
第7章 国際人材育成
第8章 国際報酬
第9章 国際人事評価
第10章 国際労使関係
第11章 海外派遣者のマネジメント
第3部 スペシャル・トピックス
第12章 戦略的国際人的資源管理
第13章 社内言語・コミュニケーション
第14章 国際的 M&A と人的資源管理
第15章 新興国発多国籍企業の人的資源管理
第16章 日本企業の国際人的資源管理)
索引
興味のある人はぜひ直接手にとってご覧いただきたく。
なぜ「経営現地化」が必要か?-欧米の多国籍企業の歴史に学ぶ
書評 『スミダ式国際経営-グローバル・マネジメントの先進事例-』(桐山秀樹、 幻冬舎メディアコンサルティング、2010)
・・「社長は、グローバルよりもトランスナショナル(trans-national)という表現を使うが、これは直訳すれば国境を越えたという意味だ。たとえ英語を共通言語にして人事交流を活発にしたとしても、国ごとに固有の文化や価値観に違いが残るのは当然だし、また現実のビジネスにおいては通貨も違えば、国によって法律や規制が異なるので、これを乗り越えるためには多大な経営努力が必要になるということなのだ」
書評 『ゲームのルールを変えろ-ネスレ日本トップが明かす新・日本的経営-』(高岡浩三、ダイヤモンド社、2013)-スイスを代表するグローバル企業ネスレを日本法人という「窓」から見た骨太の経営書
・・スイスのグローバル企業の日本法人は初めて日本人になった
書評 『ターゲット-ゴディバはなぜ売上2倍を5年間で達成したのか?-』(ジェローム・シュシャン、高橋書店、2016)-日本との出会い、弓道からの学びをビジネスに活かしてきたフランス人社長が語る
・・アメリカのグローバル企業の日本法人トップはフランス人
書評 『道なき道を行け』(藤田浩之、小学館、2013)-アメリカで「仁義と理念」で研究開発型製造業を経営する骨太の経営者からの熱いメッセージ
・・稲盛哲学をアメリカで実践する日本人経営者
NHKスペシャル 「“中国人ボス”がやってきた-密着 レナウンの400日」(2011年10月23日) を見ましたか?
・・外資系企業の傘下に入る日本企業。外資は欧米系だけではない
書評 『誰も語らなかったアジアの見えないリスク-痛い目に遭う前に読む本-』(越 純一郎=編著、日刊工業新聞、2012)-「アウェイ」でのビジネスはチャンスも大きいがリスクも高い!
書評 『村から工場へ-東南アジア女性の近代化経験-』(平井京之介、NTT出版、2011)-タイ北部の工業団地でのフィールドワークの記録が面白い
・・経営する側ではなく、経営される側のローカル従業員たちはどう考えているかがわかる内容
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end