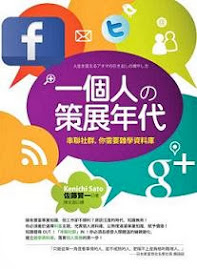「失敗学は創造学」といってよい。失敗は成功の母。自らの失敗だけでなく、知識化された他社の経験に学ぶことによって、成功への道は拓かれる。「失敗学は危機管理学」でもある。
1つの事故の背後には29のクレームがあり、その背後には300のまずいと思った体験がある、というハインリヒの法則が紹介されているが、失敗情報をきちんと管理して、「知識化」していれば大きな事故は防げるのである。これは技術の世界だけでなく、経営にも一般的にあてはまることだ。
「知識化」がきちんとなされている状況になってはじめて、知恵の伝承もなされる。
「体感」することの重要性。何も自分が「体験」しなくてもいいのである。知識化された失敗情報を自分の身に引きよせて「体感」すればいい。
『社長失格』(1998年)の著者である板倉雄一郎氏の失敗体験も、知識化されたことによって、日本語をよめるわれわれの共有財産となっているのである。
(初出情報 2001年3月28日 bk1に投稿掲載)
http://homepage2.nifty.com/kensatoken/sub2.dokudanhenken.html
目 次
プロローグ 失敗に学ぶ
第1章 失敗とは何か
第2章 失敗の種類と特徴
第3章 失敗情報の伝わり方・伝え方
第4章 全体を理解する
第5章 失敗こそが創造を生む
第6章 失敗を立体的にとらえる
第7章 致命的な失敗をなくす
第8章 失敗を生かすシステムづくり
エピローグ 失敗を肯定しよう
著者プロフィール
畑中洋太郎(はたなか・ようたろう)
1941年生まれ。東京大学工学部機械工学科修士課程修了。現在東京大学大学院工学系研究科教授。専門はナノ・マイクロ加工学、知能化加工学、創造的設計論。編著書に『実際の設計』『続々・実際の設計-失敗に学ぶ-』(日刊工業新聞社)、著書に『設計の方法論』(岩波書店)など。(単行本出版当時のもの)。『続々・実際の設計-失敗に学ぶ-』には、『失敗学』の原型であり、機械工学の設計における失敗事例が多数収録されている。
<書評への付記>
2001年に執筆した書評を再録した。この本は「失敗学」の出発点であり原点である。あらためて「古典」となった本書を振り返るために、ここに掲載することにした。(2014年3月11日 「3-11」から3年後)
<ブログ内関連記事>
最悪の事態を「想定」する-人もまた「リスク要因」であることを「想定内」にしておかねばならない!
「天災は忘れた頃にやってくる」で有名な寺田寅彦が書いた随筆 「天災と国防」(1934年)を読んでみる
「ハインリッヒの法則」 は 「ヒヤリ・ハットの法則」 (きょうのコトバ)
「天災は忘れた頃にやってくる」で有名な寺田寅彦が書いた随筆 「天災と国防」(1934年)を読んでみる
「ハインリッヒの法則」 は 「ヒヤリ・ハットの法則」 (きょうのコトバ)
「痛み」から学び、イマジネーションによって組織で共有する「組織学習」が重要だ!
Παθηματα, Μαθηματα (パテマータ・マテマータ)-人は手痛い失敗経験をつうじて初めて学ぶ
書評 『不格好経営-チームDeNAの挑戦-』(南場智子、日本経済新聞出版社、2013)-失敗体験にこそ「学び」のエッセンスが集約されている
Παθηματα, Μαθηματα (パテマータ・マテマータ)-人は手痛い失敗経験をつうじて初めて学ぶ
書評 『不格好経営-チームDeNAの挑戦-』(南場智子、日本経済新聞出版社、2013)-失敗体験にこそ「学び」のエッセンスが集約されている
書評 『反省させると犯罪者になります』(岡本茂樹、新潮新書、2013)-この本をいかにマネジメントの現場に応用するか考えるべき
(2012年7月3日発売の拙著です)
Tweet

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
end
(2012年7月3日発売の拙著です)
Tweet

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
end