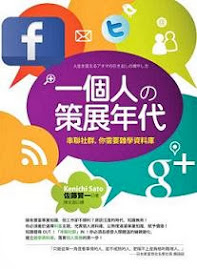「時間資本主義」というと大げさなタイトルだが、「時間価値」といえばピンとくるかもしれません。あるいは、「カネ」ではなく「時間」そのものが「資本」となる、という意味の「時間資本」なら理解できなくはないでしょう。「主義」は余計です。
この本にはとりたてて目新しいことが書いているわけではありません。議論に生煮えの点が目立ちますし、本論とは関連性の薄い教養ひけらかし的な側面も余計だと感じられます。とはいえ、アタマの整理には役立つ本だといえます。
本書のキモは、「すきま時間」×「スマホ」=時空ビジネス という一行に尽きるといっていいかもしれない。
スマホの普及で「すきま時間」や「細切れ時間」の切り売りが可能となったことは重要ですが、ポイントを稼いで小遣いにする、「すきま時間」を利用したビジネスの実例についてもっと具体的に紹介してもらったほうがよかったでしょう。
本書には言及はありませんが、もともと大型コンピュータの時間貸しなど、固定費比率の高いビジネスが稼働率を上げるために「すきま時間」を切り売りするビジネスは存在していました。「すきま時間」を売り側にとっては固定費がカバーでき、買う側にとっては固定費負担のない適正価格での利用が可能となるので、需要サイドと供給サイドと利害が一致するわけです。
本書に登場しないものとしては、たとえばネットアンケートのマクロミルなど。あるいはアマゾンやヤフーなどに「出店」して無店舗販売で商品を売るなども、売る側の立場からみれば「すきま時間」で顧客対応するわけですから、広い意味では「すきま時間」商売のなかに加えていいような気もします。
人間というのは、自分にとっては必要悪だが、無駄と思える時間は徹底的に短縮化したいと思う一方、自分がこだわりたいものに対しては、それを無駄とはけっして考えないという傾向があります。前者が「すきま時間」ビジネス利用の動機だとすれば、後者はいわゆる「時間消費」というやつでしょう。時間は限られているのです。モノよりコトの時代なのです。
節約できる時間は徹底的に節約する、これに対応できるのはアマゾンなどの一部の大企業に絞り込まれてくる。効率性を徹底追求できるのは、企業規模が大きく飽くなき効率追求に資本投下できる企業でなくては不可能です。しかも、大企業どうしの競争は激烈なものになります。いわゆる血で血を洗う「レッドオーシャン」です。「時間競争」の勝者は一部の大企業に集中するのは当然です。
ですが一方、「時間消費」への対応は、需要サイドの個々人のニーズが個別性が高いので基本的に一対一の対応にならざるをえませんい。したがって、個別需要に対応することのできる小回りのきく小企業や個人でもプレイヤーとして活躍できるわけです。
本書は、ビジネス書というよりも、「勤勉」に代表される「近代的な価値観」が融解していくなかで生きていかなくてはならないビジネスパーソンにとっての、生き方の方向性について語った自己啓発系(?)の内容といったほうがいいでしょう。
その主要なポイントは、いかに「時間リッチ」になるか、ということにあります。
幸福の尺度を時間とカネの二軸で考えてみると面白い。それが本書151ページに登場するマトリクスです。「時間リッチ」で「マネーリッチ」(=おカネ持ち)な人だけでなく、「時間リッチ」だが「マネープア」(=おカネがない)の人も幸福度が高いのに対し、「マネーリッチ」だが「時間プア」な人も、「マネープア」でしかも「時間プア」な人もまた幸福度が低い。
おカネがなくても「時間」があれば幸せ。さらにおカネがあれば、なお幸せ。おカネもちであろうとなかろうと、時間に余裕があって、自分の好きなことに時間が使える人は幸せ度合いが高いということですね。もちろん、ここでいう「時間」とは、その本人にとっての主観的なものですから、定量的に計測できる長さの時間ではありません。
高学歴で大企業に勤務する人が多い、「マネーリッチ」だが「時間プア」な伝統的エリートは、今後ますます給与水準は下がっていくのは、著者がいうように避けられないでしょう。いくらビジネス書を読んで勉強してまじめに働いても未来はないということです。いくらビジネス書を読んで仕事の効率性はあがっても、近代「後」に必要とされるクリエイティブな能力とはほど遠いのです。遊んでいないと、よい発想は生まれてきません。
近代的な価値観が融解したあとは、公私混同、つまりワークとライフは融合して分離不能なものとなる。アイデアを生み出すには、よい意味の公私混同が必要なことは、これまでも語られてきたことえあり、わたし自身も2012年に出版した拙著『人生を変えるアタマの引き出しの増やし方』(こう書房、2012)に書いているとおりです。
「近代」がすでに終わっている現状について、アタマで整理するために流し読みしてみるとよいでしょう。
目 次
いま、なぜ「時間資本主義」なのか?
第1部 時間資本主義の到来
第1章 人類に最後に残された制約条件「時間」
第2章 時間価値の経済学
第3章 価値連鎖の最適化から1人ひとりの時間価値の最適化へ
第2部 時間にまつわるビジネスの諸相
第4章 時間そのものを切り売りする
第5章 選択の時間
第6章 移動の時間
第7章 交換の時間
第3部 あなたの時間価値は、どのように決まるのか
第8章 人に会う時間を作れる人、作れない人
第9章 公私混同の時代
第10章 時間価値と生産性の関係
第4部 時間価値を高めるために─場所・時間・未来
第11章 時空を超えて
第12 章 巨大都市隆盛の時代
第13章 思い出の総和が深遠な社会へ
結局のところ、時間資本主義とはいかなる時代なのか
あとがき
参考文献
著者プロフィール
松岡真宏(まつおか・まさひろ)
フロンティア・マネジメント代表取締役。東京大学経済学部卒業後、野村総合研究所やUBS 証券などで、流通・小売り部門の証券アナリストとして活動。UBS 証券で株式調査部長に就任後、金融再生プログラムの一環として設立された産業再生機構に入社し、カネボウやダイエーの再生計画策定を担当。両社では取締役に就任し計画実行に携わる。2007 年に弁護士の大西正一郎氏と共同で、フロンティア・マネジメント株式会社を設立し、共同代表に就任。国内外で、経営コンサルティング、M&A 助言、企業再生を軸とした経営支援を行う。著書に『小売業の最適戦略』(日本経済新聞出版社)『百貨店が復活する日』(日経BP 社)『問屋と商社が復活する日』(同)『逆説の日本企業論』(ダイヤモンド社)、『ジャッジメントイノベーション』(同、共著)がある。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)
<ブログ内関連記記事>
「ワークライフバランス」について正確に理解すべきこと。ワークはライフの対立概念ではない!?
書評 『10年後に食える仕事 食えない仕事』(東洋経済新報社、2012)-10年後の予測など完全には当たるものではないが、方向性としてはその通りだろう
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end