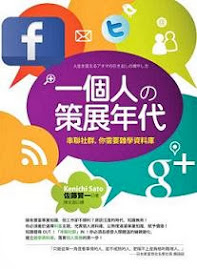先週木曜日(2013年10月25日)、大阪リッツカールトンで発覚したのが「メニュー誤標示」問題。
行動規範としての「クレド」(=信条)を従業員に徹底させることで、すぐれたサービスを実践する会社として著名なアメリカ系の高級ホテルがリッツ・カールトンですが、まことにもって悲しいかな、「ブルータス、お前もか!」と言いたくなってしまう出来事です。
日本経済新聞に掲載された記事「リッツ大阪でも誤表示 公表なしにメニュー訂正」(2013年10月25日)から一部引用しておきます。
報道各社の取材に応じたオリオル・モンタル総支配人によると、ホテル内のレストランでブラックタイガーを車エビ、バナメイエビを芝エビとしてそれぞれ提供していたほか、レストランやラウンジで容器詰めのストレートジュースを「フレッシュジュース」とメニューに表記していた。・・(中略)・・「あってはならないことで深刻に受けとめている。誤表示が起きた詳しい経緯について今後調査する」とした。
接客にかんしては定評のあるリッツカールトンですが(・・わたしも大阪リッツカールトンには一回だけですが宿泊したことがあります)、お客様とはダイレクトに接触する接客ポジション以外では、「クレド」が徹底していなかったということでしょうか・・・?
まことにもって残念としかいいようがありません。
■短期的なコスト削減がブランド毀損(きそん)を招く
企業経営にとっての最大の難問の一つは、短期利益と長期利益の折り合いをどうつけるかにあります。これは企業業績にかかわるものであると同時に企業倫理にもかかわる問題です。
おそらくホテルのレストランの現場においては、コストダウン要請プレッシャーがそうとう強かったのではないかと推測されます。
大阪リッツ・カールトンは米本社の直営ではなく、阪急阪神グループがオーナーです。阪急ホテルでも「誤表示」問題が表沙汰になっています。リッツ大阪のオーナーである阪急グループとしての経営姿勢が問われますが、リッツ・カールトンのブランドイメージに傷を付けた責任も問われることでしょう。
短期利益にたいして、ブランドはまさに長期利益の源泉。企業がサステイナブル(=持続可能)な存在として利益を指し続けていくために大事なのがブランドです。
ブランドに体現された信用を築き上げるのには長い時間がかかるのに対し、信用が失われるのは一瞬の出来事です。なぜなら、ブランドは法的には企業の所有物であっても、あくまでも顧客のアタマのなかにあるものだからです。顧客の信用があってこそブランドは意味をもつのです。
つまり、短期利益追求姿勢と長期利益実現のコンフリクト(葛藤)が不祥事として表面化したということなのです。
さらなるブランド毀損(きそん)がリッツ・カールトン全体に波及するのを防ぐため、リッツの米本社サイドがどう判断し動くか要注視でありましょう。
■リッツ・カールトンといえば「クレド」
「クレド」とは、米国の高級ホテルチェーンのリッツ・カールトン・ホテルが、全従業員に配布し、徹底させている「理念や使命、サービス哲学を凝縮した不変の価値観」のことです。
しかし今回明らかになったのは、たとえ「クレド」そのものは立派な内容でも、それを実践するのはあくまでもヒトであるということ、しかも全従業員が確実に実践できいていないのであれば、いくら立派な「クレド」であっても額縁に入って飾られた「経営理念」となんら変わらないということです。
顧客を中心にしたステークホールダーとのコミュニケーションにおいて、「ブランドの約束」が守れなかったということなのです。
コスト削減要請が無言のプレッシャーとして存在したのではないかと推測されますが、だからといってけっして許されることではありません。故意だったかどうかは外部からはわかりませんが、結果としてお客様をあざむいていたわけですから。
裏切られた思いをしているのはリッツ・カールトンのファンであるリーピーターの皆さんだと思いますが、それと同じくらい残念で悔しい思いをしているのは従業員のみなさんではないかと想像されます。
徹底的な調査を行ったうえで、「クレド」をふたたび徹底させるべく、一から出直してていただきたいものです。
■行動規範を組織全体に徹底させるには組織内コミュニケーションがいかに重要か
それにしても、行動規範を組織全体に徹底させるのは、いかに難しいことか・・・。あのリッツ・カールトンですら、こうなのですから。
「クレド」にかんしては経営学のテキストでよく引き合いに出されるアメリカの医薬品メーカーのジョンソン・アンド・ジョンソン(J&J)があります。経営理念の浸透によって危機管理において初期動作を成功させた事例です。
1982年、ジョンソン・アンド・ジョンソンが販売する解熱剤「タイレノール」に何者かがシアン化合物を混入。服用した7人が死亡する事件が起きたのですが事件発生後1時間ほどで対応を開始、「シアン化合物混入の疑いがある」とすぐに情報を公開し、製品を回収。異物混入を防ぐ対策を取ったのがその内容です。徹底した情報公開と迅速な対応により問題を収束させたわけです。
そのジョンソン・アンド・ジョンソンですら、2010年には米国内で医薬品のリコール問題を引き起こしています。ヒューマン・エラーは完全に根絶できないのはいたしかたありません。
大阪リッツ・カールトンの件ですが、組織内コミュニケーションにも問題があったのではないかと推測されます。トップと現場との距離感が、どうも予想に反して存在していたのでないかという印象を受けています。
「誤(あやま)つは人のさが」という表現があるように、誰にでも安直な道を選択してしまうという誘惑にかられることも間違いを起こしてしまうこともあります。コスト削減要請を安い食材で代替してしまうという誘惑に負けてしまったかもしれません。
しかしながら、包み隠さずなんでも話し合うことができうようなコミュニケーション環境ができあがっていれば、こうした問題に直面したときに上司に相談ができたはずです。詳しい事情がわからないので何とも言えませんが。
組織内コミュニケーションの重要性をさらに真剣に捉えていただきたいものです。それがなければ、行動規範の徹底は不可能です。
世の中の経営者の皆さんは、大阪リッツ・カールトンのケースを「他山の石」として教訓を学び取るべきでしょう。
<関連サイト>
リッツ・カールトン大阪が食材を"偽装" 東京と異なる経営(ハフィントンポスト 2013年10月25日)
ホテル、百貨店で偽装を続発させた「レストラン」という世界の特殊性(財部誠一、ダイヤモンドオンライン 2013年11月8日)
阪急阪神ホテルズだけでない!メニュー表示偽装の構造問題(ダイヤモンドオンライン 2013年11月11日)
食材偽装問題の根っこは「ブランド乱立」にあり!数百ページの再発防止策より大切な“シンプルルール”――水村典弘・埼玉大学経済学部准教授に聞く (ダイヤモンド・オンライン 2013年12月18日)
・・ブランドの根幹には顧客からの「信頼」という目に見えないものがあるという原点を見つめることだ。看板に書かれた表示を「信頼」している顧客を裏切るとブランド崩壊につながる!
<ブログ内関連記事>
「ゆでガエル症候群」-組織内部にどっぷりと浸かっていると外が見えなくなるだけでなく、そのこと自体にすら気が付かなくなる(!)というホラーストーリー
クレド(Credo)とは
「風評被害」について-「原発事故」のため「日本ブランド」は大きく傷ついた
本日(2011年3月28日)は、1979年の「スリーマイル島原発事故」から22年-「想定外」をなくすのがリーダーの務め
「距離感」と「パーセプション・ギャップ」-自分にとって不利となる誤解を正すためにまず認識すべきこと
・・メニューに記載された食材と実際に使用されている食材が一致しないという「誤表示」問題の背景には、調理という専門家の世界の「常識」と世間一般の常識」とのあいだにパーセプション・ギャップ(認識ギャップ)が存在しているから
製品ブランドの転売-ヴィックス・ヴェポラップの持ち主は変わり続ける
ゼスプリ(Zespri)というニュージーランドのキウイフルーツの統一ブランド-「ブランド連想」について
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end