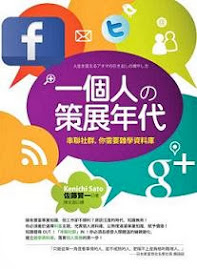人前で話すことがますます重要になってきているこの時代。
ビジンスパーソンにとってはもちろん、そうではなくてもプレゼンの重要性は増すことこそあれ、減ずることはないでしょう。
商売であれなんであれ、
人をその気にさせてアクションに向かわせることが求められる世の中だからです。
コトバをつかわずに「あうんの呼吸」で感じあうといったことは、もはや期待しないほうがいいのです。それはあくまでもごく親しい人との関係の話しであって、
見知らぬ人、たとえ知り合いであってもかならずしも友人ではない利害関係者を相手にする場合は、説得のコミュニケーションがカギになります。
世の中は変わったのです。だからコミュニケーション関連本がベストセラーになるのです。
■
類書とは違う本書の特徴
本書は、
滞日33年、合気道7段の日本通のアメリカ人が日本人向けに日本語で書いた本です。
内容紹介にはこうあります。「世界中の25000人の中で優勝したプレゼンメソッド「ワールド・クラス・スピーキング」が日本初上陸。自身も TED-X に2度登壇した著者が解説する、誰でもうまいプレゼンができる驚異のメソッド」。
「驚異のメソッド」というのは、さすがに割り引いて受け取るべきでしょうが、本を読んだ限り、
ひじょうにつかえるメソッドであることは間違いないと思います。
わたしは著者とは面識はありません。また、「滞日33年、合気道7段の日本通」というプロフィールが前面に打ち出されているわけではありませんが、読んでいて「この人はさすがによくわかっているな」と感じさせるものが、本書のすみずみからにじみ出ているのを感じました。
テクニックを書いた本ならいくらでもありますが、
この本が類書と違う点がくつかあります。
まず、
「プレゼンが上手な人の条件」がふつうのビジネスパーソンの発言とは異なることです。
「プレゼンが上手な人の条件」
1 プロフェッショナルであること
2. 女性を退屈させないこと
3. 子どもに面白いと思ってもらえること
4. 動物ともコミュニケーションがとれること
これwだけ読むと「おんな子ども」という日本語表現を想起してしまいますが、著者の意図は「上から目線」や性差別とは関係ないと、好意的に受け取っておきましょう。
そもそも
プレゼンは、論理もさることながら感情に訴えることが大事。そうでないと伝えたいことが伝わらないからですし、著者自身、子どもに絵本を読み聞かせることがプレゼンの練習になると書いています。一般的に共感話法を得意とする女性がプレゼンターとなる場合は、あえて強調するまでもないことでしょう。
つぎに、スティーブ・ジョブズなどの
有名人のプレゼンではなく、自分自身の Ted-Xのプレゼンを教材に使っている点が類書とは違う点です。本書を読む前に、19分弱のプレゼンビデオをみるべきでしょう。著者自身が日本語でプレゼンしているので安心して視聴してみてください。
⇒
世界最高のプレゼン術 (公式サイト)
著者は「コンテツが9割」と強調していますが、『伝え方が9割』という本がベストセラーになって以来、「●●が9割」というフレーズが流行してますね。プレゼン用のコンテンツのつくりかたについては、これは直接本文を読んでいただきたいと思います。
この本の特色は、
プレゼンにおけるボディ・ランゲージの重要性にもあると思います。さすがに合気道七段だなと思わせるものがあります。(ちなみに、わたしは合気道二段です)。
■
究極のプレゼンは「スライドゼロ」!
わたしがもっとも共感するのはテクニックもさることながら、
著者の姿勢というか哲学です。
究極的にはプレゼン資料は「スライドゼロ」を目指すべきという姿勢(P.67、166)には激しく同意します。
スライドや画像、そして凝りに凝った動画は手間とカネを使えば作成可能です。しかし、これらのツールに頼るのは、自分のプレゼン能力が低いからだと思うべきなのです。
自分が語るコトバとジェスチャーだけで聴衆をその気にさせ、巻き込むことが究極的には可能なはずなのです。英語でいえば Doinjg よりも Being ということでしょう。その人の存在そのものが何かを語るというところまで目指したいものです。
たいへん困ったことにプレゼン=パワーポイントと思い込んでいる残念な人たちがビジネスパーソンに増えていますが、
目指すのは「スライドゼロ」といいうことはつねにアタマのなかに入れておきたいものです。
もちろん、すぐには実行できいないので、
スライドは最低限必要な枚数に絞り込み、最小限必要な情報まで圧縮することから始めるべきでしょう。目指すべきところが明確になれば、そのための訓練も意味あものになるはずですね。
著者がいうように、演台も水もすべて片づけ、つねに両手をフリーにしておくことも大事です。これならすぐにでも実行できますね。まずはカタチから入る、これはきわめて重要です。
■
日本人の「強み」をもっと意識して前面に出すべき
著者のいうテクニックや姿勢は、
「シンプル・イズ・ベスト」という簡潔明瞭さを追求したミニマリズムであり、
本来は日本人の美意識にかなうはずのものです。俳句がまさにその代表例ですね。
でもなぜか不思議なことに、いまの日本人はできていません。プレゼンというコトバがまだ完全に日本語として熟していないからかもしれません。
「シンプル・イズ・ベスト」を説く著者は、ある意味では、日本人に本来の日本人の特性を思い出させ、
日本人が自分の「強み」を生かすことが、ワールドクラスのプレゼンのための近道だと説いていると捉えて間違いないでしょう。
「5C」でストーリーをつくる、10分で1つのポイントを伝える、クロージングは質疑応答のあとに、「タイムライン」というテクニックを活用するなど、さまざまなテクニックが紹介されています。
オープニングとクロージングの重要性を説く著者ですが、なぜかこの本にはクロージングがないのが不思議です。なんだか尻切れトンボのような感じで終わってしまいます。
オープニングは日本語でいえば「つかみ」であり、本でいえば「はじめに」や「まえがき」に該当します。本書の「はじめに」も、セオリーどおりの「つかみ」になっていると言っていいでしょう。
ですが、日本語の本は「あとがき」でクロージングをするということを著者は体感していないのかもしれません。質疑応答のあとにクロージングするという手法が本書にかんしては実践されていません。
英語の本には「「結論」があっても「あとがき」はありません。しかし、
日本語の本では「あとがき」で「本文」に書いたことをあらためて要約したり、本文には書かなかったことを書いて情に訴えたりしながらクロージンにもっていくのが「常識」です。日本語世界では余韻が大事なのです。
その意味では、画竜点睛ではないかな? 著者は無意識のうちにふだん読んでいる英語の本の「常識」が出てしまったのかもしれません。ある意味、
最後の最後で貴重なアドバイスを反面教師として逆説的に(!)与えてくれる本でもありました。
本書で紹介されている
テクニックやマインドセットは実地に試してみてこそ意味をもつもの。ぜひ
自分のアタマだけでなく、自分のカラダもつかって本書に書かれた内容を体感してみることを薦めます。
さまざまな「学び」を得ることのできる本としてお薦めします。
PS. この書評は、R+(レビュープラス)さまより献本をいただいて執筆したものです。
目 次
はじめに 日本人の99%のプレゼンは間違っている
ワールド・クラス・スピーキング創始者 監修者クレッグ・バレンタインより
序章 これが「ワールド・クラス・スピーキング」だ
第1部 コンテンツをつくる
第1章 柱となるコンテンツを整理する
01 伝えたいポイントを盛り込みすぎない
02 コンテンツは簡潔にまとめる
03 スライドはいきなりつくらない
第2章 オープニングからクロージングまでの流れをつくる
04 オープニングはもっとも重要なコンテンツ
05 コンテンツをつくる重要なポイント
06 大切にしたいクロージング
第3章 魅力的なコンテンツをつくる
07 ストーリーでプレゼン力を高める
08 具体的にどうやってストーリーをつくるか
09 聞き手をワクワクさせるコンテンツのつくりかた
10 聞き流されないコンテンツのつくりかた
11 コンテンツがみるみる生まれる魔法の方法
第4章 スライドをデザインする
12 スライドは「シンプル」で勝負せよ
13 【実践編】コンテンツを磨く
第2部 伝え方を磨く
第5章 もっとよく伝わる体の使い方
14 プレゼンは感情・感覚に訴える
15 正しい姿勢がプレゼンを成功させる
16 プレゼンで大切な舞台の使い方
第6章 もっとよく伝わる環境のつくりかた
17 プレゼンはリハーサルが9割
18 プレゼンで大切な木っ気手への言葉かけ
19 聞き手との一体感を獲得する
20 【実践編】4つの伝え方の柱
著者プロフィール
ウィリアム・リード(William Reed)
アメリカ出身。アーラム大学(アメリカ)で日本語と日本文化を研究し、在学中に早稲田大学に留学。その後ミズーリ大学大学院修士課程修了(専攻は教育学など)。合氣道七段、書道の師範であり、日本通。トーストマスターズのワールドチャンピオンスピーカーになったクレッグ・バレンタイン(Craig Valentine)氏に師事し、2009年に世界で第一号のワールドクラス・スピーキングの認定コーチになる。現在は、ワールドクラス・スピーキングの日本の拠点として、EMC Quest,K.K.の会長を務め、企業や個人向けのセミナーやコーチングプログラムを日本語と英語で設けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。
<関連サイト>
世界最高のプレゼン術 (公式サイト)
<ブログ内関連記事>
書評 『思いが伝わる、心が動くスピーチの教科書-感動をつくる7つのプロセス-』(佐々木繁範、ダイヤモンド社、2012)-よいスピーチは事前の準備がカギ!
『伝え方が9割』(佐々木圭一、ダイヤモンド社、2013)-コトバのチカラだけで人を動かすには
書評 『小泉進次郎の話す力』(佐藤綾子、幻冬舎、2010)-トップに立つ人、人前でしゃべる必要のある人は必読。聞く人をその気にさせる技術とは?
合気道・道歌-『合気神髄』より抜粋
カラダで覚えるということ-「型」の習得は創造プロセスの第一フェーズである
(2012年7月3日発売の拙著です)

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
end