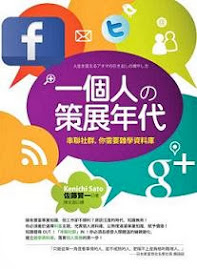■
「学ぶとは真似ぶなり」とは、個人でも会社でも同じこと。模倣するための作法とは?
本書は、
すぐれた会社はすぐれた模倣を行っていることについて書かれた一般向けの経営書です。
クロネコヤマト、スターバックスとドトールコーヒー、ジョンソン&ジョンソン、グラミン銀行などの具体的な事例をつかいながら、すぐれた会社が、
何をどう模倣しているのか、あるいは反面教師として経営戦略をつくりあげたかを分析したものです。
模倣というと上品な響きだが、英語でいえばイミテーション、本質的には真似(まね)と同じです。
日本語では
「学(まな)ぶとは真似(まね)ぶなり」という表現があるように、
「模倣すなわち学習」のことです。
子どもが大人を真似るように、何事もお手本となるモデルがなければ、独自性も創造性もあったものではありません。いや、
真似して自分のあったものを取捨選択して身につけることじたいが、じつはきわめてクリエイティブな行為なのです。
模倣は基本的には個人レベルで行われるものであるが、会社レベルでも行われます。
もちろん、会社を動かしているのは経営者や個々の従業員である以上、模倣のプロセスはそれほど簡単ではありません。
本書で行われているのは、基本的には経営戦略をつくって実行させる立場にある経営者レベルのものです。著者は、本書において、経営者がみずから書いた本を材料にして事例分析を行っています。
本書は経営書ではありますが、
経営者が書いたビジネス書などを読む際のガイドにもなっています。経営者が書いた回想録や経営書を読むことじたい、じつはビジネスパーソンにとっては、ある種のすぐれた模倣となるべきなのです。読者は、自分に必要なもの本から読み取って模倣するための手引としても活用すべきでしょう。
ただし、実務家である経営者や経営コンサルタントとは違うなと思う記述もすくなくありません。分析して見せるまではいいのですが、ではどう取り組むかまではあまり書かれていないためです。その点はあまり期待せず、割り引いて読むことをすすめたいと思います。
マネジメント専門書を読むのはハードルが高いと、ためらっている若手ビジネスパーソンにはぜひ手にとって通読してみるといいと思います。
<初出情報>
■bk1書評「「
学ぶとは真似ぶなり」とは、個人でも会社でも同じこと。模倣するための作法とは?」投稿掲載(2012年4月4日)
■amazon書評「「
学ぶとは真似ぶなり」とは、個人でも会社でも同じこと。模倣するための作法とは?」投稿掲載(2012年4月4日)
*再録にあたって一部加筆修正した
目 次
まえがき 模倣のパラドクス
第1章 「天才のなぞかけ」-メタファーとイノベーション
第2章 「インドの露天商」-模倣すべき本質をモデリングする
第3章 「クロネコの革命」-4つの要素と5つのステップ
第4章 「2つのカフェ」-模倣の創造性
第5章 「4人の教師」-誰をどのように模倣するのか
第6章 「守破離」-手本と現実のギャップを越える
第7章 「わな」-模倣できそうで模倣できない会社
第8章 「反転」-逆発想のモデリング
第9章 「作法」-倣い方を倣う
あとがき 経営書を「消費財」で終わらせないために
著者プロフィール
井上達彦(いのうえ・たつひこ)
早稲田大学商学学術院教授。1997年神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了、博士(経営学)。広島大学社会人大学院マネジメント専攻助教授、早稲田大学商学部助教授(大学院商学研究科夜間MBAコース兼務)などを経て、2008年より現職。2011年9月より独立行政法人経済産業研究所(RIETI)ファカルティフェロー、2012年4月よりペンシルベニア大学ウォートンスクール・シニア・リサーチフェローを兼務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの
<書評への付記>
■
お手本の模倣(=真似)はすべての出発点
社会人になる前のことですが、大学の卒論を書く際に言われたことをいまも思い出します。
ゼロからオリジナルな論文など書けるわけがないので、自分が設定したテーマにもっとも適合した論文を探し出してきて、それを徹底的に読みむこ真似ること。そのうえで、卒論を書き始めてみるように、と。
すべてはお手本を真似るということから始まるのです。真似するのです。
著者も一章をさいて説明していますが、日本の武道や芸事には、
「守破離」という「型」を身につけるためのモデルが古くから確立しています。まずは師匠を徹底的に真似てから、あえてその教えを破り、最終的には独り立ちして自分の型をつくりあげるというモデルです。
本書で面白いと思ったのは、
西洋の弁証法モデルもまた「正反合」と三段階で物事を説明していること。
「守破離」よりもアンチテーゼ的な要素が濃いですが、構造としてはよく似ています。
著者のいう
「正転模倣」が「守破離」であれば、
「反転模倣」は「正反合」に対応しています。
著者は、
遠いところからポジティブな模倣をすることを「正転模倣」、
近いところから反面教師として模倣することを「反転模倣」と、聞き慣れないコトバをつかって説明していますが、意味したことは理解できる。
「反面教師」とは「人の振り見て我が振り直せ」ということです。
なにごとも自分で体験できればそれに越したことはありませんが、じっさいには時間の関係からそれは不可能です。
実体験からの学びを「経験学習」といいますが、
「代理学習」(観察学習、間接経験学習)もまた必要なのはそのためです。
■
さらに必要なのは「組織変革」の視点
ひじょうに面白いポイントから書かれていますが、
組織というものは経営者の意向に従って動くものだという単純なモデルに基づいているような印象を受けます。
経営者は会社を自分の考える方向に引っ張っていくことができますが、じっさいに組織内で起こっていることは、それほど単純ではありません。
じっさいは、それぞれべつの思惑をもつ個人が、同じ方向性(=経営戦略)というワクのなかで、
一人一人のメンバーの行動が、複雑系のなかで交差しながら、前進したり後退しながら前に進んでいるというのが会社組織の実態です。
模倣というのはまず何といっても個人レベルの問題であり、
個人レベルの模倣がヨコ展開や反面教師をつうじて拡散、伝播していくという視点を忘れてはいけません。
一人の人間の脳内で起こっているプロセスと、複数の人間のあいだで起こるプロセスが違うことについて、深く考えておかねばならないのです。これは、経営者がおうおうにして間違いやすいポイントです。
学者の分析は分析どまりでプラクティカルではないという感想をもつのは、そういう理由です。とはいっっても、学者の役割を否定しているわけではありません。要は、学者もハサミも使いようだ、ということです。
<ブログ内関連記事>
書評 『プロフェッショナルを演じる仕事術』(若林計志、PHPビジネス新書、2011)-「学ぶとは真似ぶなり」という先人の知恵を現代風にアレンジした本・・「守破離」のポイントは同じ
書評 『絶対の自信をつくる 3分間トレーニング』(松尾昭仁、あさ出版、2011)・・カタチから入る誰でもできる方法について書かれたもの。この本は初級者向け
What if ~ ? から始まる論理的思考の「型」を身につけ、そして自分なりの「型」をつくること-『慧眼-問題を解決する思考-』(大前研一、ビジネスブレークスルー出版、2010)
・・「守破離」についてわたしのコメントが書いてある。あわせてお読みいただきたい
「学(まな)ぶとは真似(まね)ぶなり」-ノラネコ母子に学ぶ「学び」の本質について
カラダで覚えるということ-「型」の習得は創造プロセスの第一フェーズである
「三日・三月・三年」(みっか・みつき・さんねん)
「地頭」(ぢあたま)について考える (1) 「地頭が良い」とはどういうことか?
「地頭」(ぢあたま)について考える (2) 「地頭の良さ」は勉強では鍛えられない
書評 『ヒクソン・グレイシー 無敗の法則』(ヒクソン・グレイシー、ダイヤモンド社、2010)-「地頭」(ぢあたま)の良さは「自分」を強く意識することから生まれてくる
世の中には「雑学」なんて存在しない!-「雑学」の重要性について逆説的に考えてみる
・・本書でも取り上げられている藤田田(ふじた・でん)について
 ケン・マネジメントのウェブサイトは
ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
end