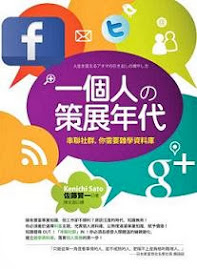知らない世界を知るというほど面白いことはない。わたしにとっては、「花街」のことは、ほとんど未知の世界に等しい。そもそも「花街」と書いて「かがい」と読むということすら知らなかったのだ。ずっと「はなまち」だと思い込んでいた。
『「一見さんお断り」の勝ち残り経営-京都花街お茶屋を350年繁栄させてきた手法に学ぶ-』(髙橋秀彰、ぱる出版、 2017)の存在を知ったのは、「レビュープラス」から書評執筆の打診があったからだ。二つ返事で引き受けたのは、自分にとってよく知らない世界を垣間見るチャンスになると思ったからでもある。
「一見(いちげん)さんお断り」というフレーズは、すくなくとも日本人なら、大人であれば知らない人はいないのではないのだろう。それほど京都のイメージを代表するものはないのではないかと思う。
「一見さんお断り」とは、閉鎖的だとか、敷居が高いとか、上から目線だとかいうネガティブなイメージがつきまとっており、「京のぶぶ漬け」のイメージともあいまって、なんだか取っつきにくいイメージを固定化させてしまっている。
だが、「一見さんお断り」のシステムとは、紹介がなければ入会できない「会員制クラブ」と考えれば、なんとなく理解できるような気もしてくるのである。会員として受け入れられれば、クラブの内部は、会員にとっては、きわめて居心地のよい世界である、ということであろう。
そもそも、「一見さんお断り」は不文律のルールであり、「京都花街」には明文化されたルールがあるわけではないし、「京都花街」の内側の人は、みずからについてほとんど語ることはない。「会員制クラブ」である以上、それは当然のことだろう。
著者は、そんな「会員制クラブ」の世界に入会を許され、身銭を切って遊ぶお客としてお客として中の世界を観察してきた人だ。しかも、公認会計士だが報酬を支払っていただく「クライアント」としてつきあってきたのではなく、あくまでも身銭を切った「個人」としてかかわってきた人である。お金をもらう側と、支払う側とでは、おなじ対象であっても、真逆の姿が見えてくるはずだ。
「花街」とは、お座敷を企画コーディネートし、芸妓(げいこ)や舞妓(まいこ)といったたタレントを送り出す「お茶屋」を中核に、タレント事務所である「置屋」、お座敷に料理を出す「料理屋」、「仕出屋」などによって構成され、「分業」によって成り立っている高度なシステムである。こんな精緻なシステムが、350年以上にわたってつづいてきたというのは京都ならではかもしれない。
「花街」の特徴を列挙すると、こんなふうになる。
『「一見さんお断り」の勝ち残り経営-京都花街お茶屋を350年繁栄させてきた手法に学ぶ-』(髙橋秀彰、ぱる出版、 2017)の存在を知ったのは、「レビュープラス」から書評執筆の打診があったからだ。二つ返事で引き受けたのは、自分にとってよく知らない世界を垣間見るチャンスになると思ったからでもある。
「一見(いちげん)さんお断り」というフレーズは、すくなくとも日本人なら、大人であれば知らない人はいないのではないのだろう。それほど京都のイメージを代表するものはないのではないかと思う。
「一見さんお断り」とは、閉鎖的だとか、敷居が高いとか、上から目線だとかいうネガティブなイメージがつきまとっており、「京のぶぶ漬け」のイメージともあいまって、なんだか取っつきにくいイメージを固定化させてしまっている。
だが、「一見さんお断り」のシステムとは、紹介がなければ入会できない「会員制クラブ」と考えれば、なんとなく理解できるような気もしてくるのである。会員として受け入れられれば、クラブの内部は、会員にとっては、きわめて居心地のよい世界である、ということであろう。
そもそも、「一見さんお断り」は不文律のルールであり、「京都花街」には明文化されたルールがあるわけではないし、「京都花街」の内側の人は、みずからについてほとんど語ることはない。「会員制クラブ」である以上、それは当然のことだろう。
著者は、そんな「会員制クラブ」の世界に入会を許され、身銭を切って遊ぶお客としてお客として中の世界を観察してきた人だ。しかも、公認会計士だが報酬を支払っていただく「クライアント」としてつきあってきたのではなく、あくまでも身銭を切った「個人」としてかかわってきた人である。お金をもらう側と、支払う側とでは、おなじ対象であっても、真逆の姿が見えてくるはずだ。
「花街」とは、お座敷を企画コーディネートし、芸妓(げいこ)や舞妓(まいこ)といったたタレントを送り出す「お茶屋」を中核に、タレント事務所である「置屋」、お座敷に料理を出す「料理屋」、「仕出屋」などによって構成され、「分業」によって成り立っている高度なシステムである。こんな精緻なシステムが、350年以上にわたってつづいてきたというのは京都ならではかもしれない。
「花街」の特徴を列挙すると、こんなふうになる。
●顧客のニーズを叶える、完全なオーダーメイドの「個別受注生産」
●リピート客が上質な新規顧客のみを紹介するシステム
●薄利多売・価格競争・広告宣伝とは無縁の永続経営
●馴染み客、一見さんの二つのラインの明確な分離
著者は、こんな「京都花街」のシステムには、学ぶべきものが多いとしている。ある点までは、耳を傾ける意味はあると思われる。「一見さんお断り」という仕組みは、じつに魅力的だからだ。
だが、このようなシステムは一社単独では成立不可能なものであろう。シリコンバレーについてよくいわれているように、IT関連のハイテク企業は、それを成り立たせるエコシステム(=生態系)があってはじめて生存可能である。「京都花街」も、たんなる「花街」ではなく、あくまでも「京都」の「花街」という限定つきの存在だ。異なる地域の、異なる産業の、異なる企業に「横展開」できるかどうかは、そう簡単には言えないのではないだろうか。
本書のちょうど10年前に出版されている『京都花街の経営学』(西尾久美子、東洋経済新報社、2007)を読むと、「京都花街」の特殊性と普遍性がよく理解できる。350年以上の歴史をもつ「京都花街」も、時代の変化と外部環境の変化のなかで柔軟に変化し進化してきたのであって、この点を見落とすことは危険である。とくに、舞妓(まいこ)の人材育成は、時代の変化の影響を大きく受けており、かならずしも昔そのままではないという点は重要だ。
とはいえ、日本企業でも非上場の中小企業であれば、「京都花街」を構成する中小企業と共通する面も多い。「分業制」や「紹介」で仕事を回す仕組みなど、基本的には共通している。ただし、「花街」の「分業制」は「下請け制」ではなく、あくまでも水平的なヨコの関係だ。
要は、時代の変化には柔軟に対応しつつも、変えてはいけない経営の根幹と、変えてもかまわない部分はわけて考えることが大事だということだ。この点は、「京都花街」から大いに学ぶべきものがあるといえよう。
著者プロフィール
髙橋秀彰(たかはし・ひであき)
髙橋秀彰綜合会計士事務所 代表。公認会計士・税理士・宅地建物取引士。昭和40年生まれ、愛知県出身。立命館大学理工学部卒。創業当初の資金状況の苦しい中でも「一見さんお断り経営」を貫き、公認会計士であるにもかかわらず経済合理性に反するリスクを背負った経営判断を行ったことから一目置かれる信用と実績を築く。とくに他の会計事務所では手に負えない高度な案件などを得意としており、数多くの相続対策や非上場企業の株主構成の再構築、資金繰り改善の実績を持つ。また、京都花街のお茶屋では稀有な顧客として知られ、京都花街の不文律や裏事情にまで精通している。
目 次
はじめに
第1章 徹底的な顧客満足
第2章 価格競争への対応
第3章 馴染み客も一見さんも
第4章 経営者の役割
第5章 公認会計士・税理士的視点から見た日本的経営の魅力
おわりに
<ブログ内関連記事>
書評 『京都の企業はなぜ独創的で業績がいいのか』(堀場 厚、講談社、2011)-堀場製作所の社長が語る「京都企業」の秘密
書評 『「できません」と云うな-オムロン創業者 立石一真-』(湯谷昇羊、新潮文庫、2011 単行本初版 2008)-技術によって社会を変革するということはどういうことか?
書評 『全員で稼ぐ組織-JALを再生させた「アメーバ経営」の教科書-』(森田直行、日経BP、2014)-世界に広がり始めた「日本発の経営管理システム」の仕組みを確立した本人が解説
書評 『知的生産な生き方-京大・鎌田流 ロールモデルを求めて-』(鎌田浩毅、東洋経済新報社、2009)-京都の知的風土のなかから生まれてきた、ワンランク上の「知的生産な生き方」
神田・神保町の古書店街もまた日本が世界に誇る「クラスター」(集積地帯)である!
(2017年5月19日発売の新著です)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end