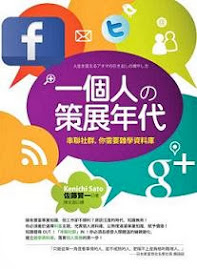富士通のスパコンが世界一になったというニュースに、ひさびさに胸躍る思いをした日本人はすくなくないと思います。
スーパーコンピュータ-「京」(けい)が世界一であった期間は、思ったよりも短かったですが、それでも世界一になったという事実を消し去ることはできません。日本人にとっては、じつにうれしい快挙でありました。
「R+ レビュープラス」から献本をいただきましたが、今回、書評を執筆したくなったのは、「外から見た富士通」という一章に寄稿された、竹内弘高ハーバード・ビジネスクール教授の文章を読みたかったからです。この一文だけでも読む価値は十分にあります。
「いまこそ日本に学べ!」と題されたこの文章のなかで、竹内教授は「失われた20年は、日本にとってはゆるやかな回復期ではなかったかもしれない」という欧米の論調の変化にふれています。
2008年のリーマンショック以後、欧州だけでなく、アメリカもまた一部のイノベーティブな企業を除いては苦しい状況にあることは言うまでもありません。そんななかで、周回遅れで再浮上してきたのが日本企業。わたしたちは、もっと自信をもっていいのかもしれません。
わたしのように組織人事を専門分野としてきた人間にとっては、富士通というと、どうしても『若者はなぜ3年で辞めるのか-年功序列が奪う日本の未来-』(光文社新書、2006)などのベストセラーをつぎつぎと発表している人事コンサルタントの城繁幸氏の著作を思い出してしまいます。
成果主義の導入が、社内で混乱を招いたことを描いた『内側から見た富士通「成果主義」の崩壊』(光文社ペーパーバックス、2004)の印象があまりにも強烈に残っているからです。城繁幸氏は、富士通の人事部にいた人です。
しかし、本書を読む限り、英国の識者二人が指摘しているように、富士通には創業当初からの「泥臭い文化」が死なずに生き続けていることがわかって、いい意味で裏切られたような感想を抱きました。
「泥臭い」は、英語の該当表現をさがせば、down-to-earth になるようです。「地についた」という意味をもつ、なかなかなかいい響きの英語ですね。これは、解説を執筆しているナレッジマネジメント論の大家・野中郁次郎(一橋大学名誉教授)のコトバを借りれば、「現場で最善の判断を下し、実行する実践知」そのものでもあるわけです。
暴走する資本主義が見失っていたものが、まだまだ日本企業には残っているわけで、この特質はけっして失ってはならないものだと、あらためて思います。自分の強みは明確に意識する必要があるのです
本書は、実行するのが困難でかつ社会的意義の大きな8つのプロジェクトにまつわる、富士通版「プロジェクトX」の活字版といった内容ですが、それぞれのプロジェクトに携わった富士通の社員のみなさんの熱い思いが行間からにじみでる好読み物になっています。
欲をいえば、富士通の海外法人や日本法人で働いている外国人社員の活躍も声として拾って欲しかったと思います。なぜなら、富士通のバリューやミッションが、どのように全世界で浸透しているかを知りたかったからです。
とはいえ、日本人の底力がここにあると示してみせた8つのストーリーを読んで、元気を取り戻したいものですね。あきらめない気持ちを持ち続けることがいかに大事を教えてくれる一冊です。
目 次
はじめに
第1章 絶対にNo.1を目指す-スーパーコンピューター「京」
第2章 覚悟を決めて立ち向かう-株式売買システム「アローヘッド」
第3章 妄想を構想に変える-すばる望遠鏡/アルマ望遠鏡
第4章 誰よりも速く-復興支援
第5章 人を幸せにするものをつくる-「らくらくホン」シリーズ
第6章 泥にまみれる-農業クラウド
第7章 仲間の強みを活かす-次世代電子カルテ
第8章 世界を変える志を持つ-ブラジル/手のひら静脈認証
寄稿 外から見た富士通
-いまこそ日本に学べ! 竹内弘高
-変革に挑む スチュアート・クレイナー/デス・ディアラブ
おわりに
解説 野中郁次郎
受け継がれてきた言葉
謝辞
著者プロフィール
片瀬京子(かたせ・きょうこ)
1972年生まれ、東京都出身。1998年に大学院を修了し、出版社に入社。雑誌編集部勤務の後、2009年からフリー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの
田島篤(たじま・あつし)
1965年生まれ。日経BP社コンピュータ・ネットワーク局プロデューサー兼 ITpro 副編集長。1989年に日経BP社入社。日経 Linux 編集長、日経ソフトウェア編集長を経て、2011年7月から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。
<ブログ内関連記事>
書評 『経営管理』(野中郁次郎、日経文庫、1985)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end