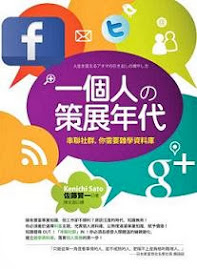マザー・テレサについては、あらためて説明するまでもないと思います。バルカン半島の小村に生まれ、インドのカルカッタ(コルコタ)で貧しい人たちのための奉仕活動に一生を捧げたカトリックの修道女です。
一方、マザー・テレサには、「貧しい人びとのなかのもっとも貧しい人びとに仕える」(to serve the poorest of the poor)というミッションを掲げた「神の愛の宣教者会」(ミッショナリー・オブ・チャリティー)を、カトリック教会の内部で新規に立ち上げ、国際的な組織に育て上げたという「企業内起業家としての側面」もあります。
それが本書のタイトルにもあるマザー・テレサCEO(最高執行責任者)ということが意味するものです。
マザー・テレサの一生は、ミッション遂行のためには万難を排して献身した人生であり、けっして平坦な道ではなかったのでした。
本書は、若き日にマザー・テレサのもとで奉仕活動を行った起業家の著者が、ビジネス上のメンターとともに書き上げた、リーダーシップのあり方の原則にかんするビジネス書です。
しかし、あたらしい事業を立ち上げ、国際的な組織に育て上げるという外面的な「成功」についてのみ語った内容ではありません。
組織のリーダーとして毎日のように直面するさまざまな課題といかに正面から向き合い、ひとつひとつ解決していったかについてのマザー・テレサ実践について、読者と一緒に考えようという姿勢に貫かれた内容になっています。
マザー・テレサのマネジメントは、著者たちによって「リーダーシップの八原則」としてまとめられています(目次を参照)。
その多くは、カトリックの修道女として生きてきたマザー・テレサならではのものですが、「原則2 天使に会うためなら悪魔とも取引しろ」、「原則4 疑うことを恐れるな」のように、あのマザー・テレサがそうだったのか(!)と驚くような原則も含まれています。いずれも起業家や経営リーダーならかならずぶつかる難問の数々。そこで語られるのはミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の重要性です。
マザー・テレサの八原則について、通り一遍の教科書的な理解に終わらせないためにも、ぜひ実際に読んで、自分のアタマで考えてみることをすすめたいと思います。できればディスカッションの材料として、一緒に考えてみることもいいでしょう。そのために必要なのは、マザー・テレサになったつもりでイマジネーションを働かせてみることです。
企業経営にかかわっているリーダーはもちろん、ありとあらゆる組織のリーダーにはぜひ読んでほしい本として推薦します。
<初出情報>
■bk1書評「あたらしい修道会を立ち上げ、国際的な組織に育て上げたマザー・テレサのマネジメント手法とは?」投稿掲載(2012年4月25日)
■amazon書評「あたらしい修道会を立ち上げ、国際的な組織に育て上げたマザー・テレサのマネジメント手法とは?」投稿掲載(2012年4月25日)
目 次
序章 マザー・テレサの原則
マザー・テレサの生涯
第1章 簡潔なビジョンを力強く伝えろ
第2章 天使に会うためなら悪魔とも取引しろ
第3章 がまん強くチャンスを待て
第4章 疑うことを恐れるな
第5章 規律を楽しめ
第6章 相手が理解できる言葉でコミュニケーションしろ
第7章 底辺にも目配りしろ
第8章 沈黙の力を使え
おわりに あなたが聖人になる必要はない
著者プロフィール
ルーマ・ボース(Ruma Bose)
起業家、投資家、アドバイザー。『マザー・テレサCEO』出版時は、ホメオパシー関連商品やビタミ
ン剤を販売するスプレーオロジー社の社長兼共同CEO。1992~93年、インドのカルカッタ(現コルカタ)で「神の愛の宣教者会」のボランティアとして、マザー・テレサと奉仕活動を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。
ルー・ファウスト(Lou Faust)
実業界で30年以上の経験をもつビジネスマン、アドバイザー。そのうち10年をソロモン・ブラザーズに勤務し、ウォール街や東京で過ごす。マネージング・ディレクターなどを務めた。『マザー・テレサCEO』出版時はエッジ・キャピタル・パートナーズLLCの共同創業者、共同経営者。大きく成長しようとする企業に経営戦略のアドバイスを行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。
<原書タイトル>
Mother Teresa, CEO Unexpected Principles for Practical Leadership, 2011
原書には索引(インデックス)がついている。最初から原書で読んだほうがいいかもしれない。ただし、日本語版よりは値段が高いが・・
<書評への付記>
「汚く稼いで綺麗に使え!」。このフレーズは、ビジネス書作家・神田正典の本にはよく引用されているが、じっさいに日本に宣教で来ていたカトリック修道会の司祭のコトバである。
しかし、この考えはきわめて重要だ。
マザー・テレサの場合は、稼いだのではなく寄付についてだが、「かならずしもキレイではないカネ」も受け入れたという。ただし、汚いカネを美名に変換する「売名行為」というロンダリングに使用されないように、見返りはいっさい拒否したという。
ミッションにブレがなければ、「悪魔と取引」することもいとわないという姿勢、これはマザーテレサに限らず、カトリック教会の長い歴史のなかで培われた智恵であるといってよいかもしれない。
このようなモラル・ジレンマは、まさに「ハーバー白熱教室」のサンデル教授によるディスカッション・テーマをほうふつとさせるが、マザー・テレサの場合もまた同様の問題に直面していたということだ。だが、これをクリアしたのは彼女一人の決断ではないと思う。伝統のチカラもあずかっているはずだ。
マザー・テレサが立ち上げた「神の愛の宣教会」(Missionary Of Charity)は、カトリック教会内のあたらしい修道会である。だから「企業内起業」(イントラプルナーシップ)といってよいのである。始まりはベンチャーであったのだ。この件については、ブログに書いた記事「アッシジのフランチェスコ (4) マザーテレサとインド」を参照していただきたい。マザー・テレサの生涯は映画化されているので、それを見るのがいちばんだろう。
なお、序文を寄せているビジネス書作家・本田直之氏も、訳文のなかでも、「マネージメント」となっているが、これはいただけない。動詞は「マネージ」と伸ばしてもいいが、名詞になったら「マネジメント」である。
間延びしていたマネージメントではなく、アクセントは文頭の「マ」に置いたマネジメントである。原則の5にもあるように、規律あるきびきびした姿勢こそ、修道院でしつけられたマザー・テレサの生活習慣に基づいた教えである。くれぐれも間違いなきよう!
著者たちがまとめた「マザー・テレサの八原則」は以下のとおりである。
*Janitor とは門番という意味。お掃除のおばさんや用務員さんなども含まれる。
<ブログ内関連記事>
アッシジのフランチェスコ (4) マザーテレサとインド
クレド(Credo)とは
「祈り、かつ働け」(ora et labora)
書評 『修道院の断食-あなたの人生を豊かにする神秘の7日間-』(ベルンハルト・ミュラー著、ペーター・ゼーヴァルト編、島田道子訳、創元社、2011)
映画 『シスタースマイル ドミニクの歌』 Soeur Sourire を見てきた
書評 『バチカン株式会社-金融市場を動かす神の汚れた手-』(ジャンルイージ・ヌッツィ、竹下・ルッジェリ アンナ監訳、花本知子/鈴木真由美訳、柏書房、2010)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end
間延びしていたマネージメントではなく、アクセントは文頭の「マ」に置いたマネジメントである。原則の5にもあるように、規律あるきびきびした姿勢こそ、修道院でしつけられたマザー・テレサの生活習慣に基づいた教えである。くれぐれも間違いなきよう!
著者たちがまとめた「マザー・テレサの八原則」は以下のとおりである。
1. 簡潔なビジョンを力強く伝えろ(Dream it simple, say it strong)
2. 天使に会うためなら悪魔とも取引しろ(To get to the Angels, deal with the Devil)
3. がまん強くチャンスを待て(Wait ! Then pick your moment)
4. 疑うことを恐れるな(Embrace the power of doubt)
5. 規律を楽しめ(Discover the joy of discipline)
6. 相手が理解できる言葉でコミュニケーションしろ(Communicate in a language people understand)
7. 底辺にも目配りしろ(Pay attention to the janitor)
8. 沈黙の力を使え(Use the power of silence)
*Janitor とは門番という意味。お掃除のおばさんや用務員さんなども含まれる。
<ブログ内関連記事>
アッシジのフランチェスコ (4) マザーテレサとインド
クレド(Credo)とは
「祈り、かつ働け」(ora et labora)
書評 『修道院の断食-あなたの人生を豊かにする神秘の7日間-』(ベルンハルト・ミュラー著、ペーター・ゼーヴァルト編、島田道子訳、創元社、2011)
映画 『シスタースマイル ドミニクの歌』 Soeur Sourire を見てきた
書評 『バチカン株式会社-金融市場を動かす神の汚れた手-』(ジャンルイージ・ヌッツィ、竹下・ルッジェリ アンナ監訳、花本知子/鈴木真由美訳、柏書房、2010)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end