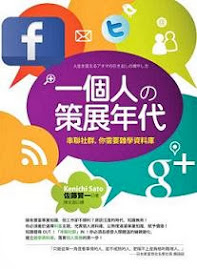2011年にジョブズが死んですでに4年近くたち、アップルの神通力にも陰りが見えてきている。画期的な製品であったスマートフォンの iPhone だが、新規参入者によってスマホはすでに普及段階を終えてコモディティ化しつつあり、PCと同様に市場はすでに飽和状態にある。
「ジョブズ亡き後のアップル」については誰もが関心のあることだろう。そのテーマに正面からがっぷりと取り組んだのが、日本生まれのジャーナリストのケイン岩谷ゆかり氏である。「著者前書き」によれば、岩谷氏はかつて日本国内で産業記者としてソニーを担当していたという。
創業者がいなくなったソニーが衰退していくのを目の当たりにしている。それだけに、今回会社トップが創業者から別の人に変わる、しかも、事業環境がどんどん複雑になっていくなかでトップが交代するという難しい事態にアップルがどう対処するのか、強く興味を牽かれた。
原題は Haunted Empire: Apple After Steve Jobs, by Yukari Iwatani Kane, 2014、直訳すれば『悩まされる帝国-スティーブ・ジョブズ後のアップル-』となる。あるいは『取り付かれた帝国』。Haunted House とはお化け屋敷のこと。死せるジョブズの影を払拭できないという意味だろうか? 英語の意味は多義的なので、なかなか適切な訳は探しにくい。
56歳という早すぎるカリスマの死のすこし前から始まる記述は、ガンをわずらって衰弱していくジョブズ自身について書かれており、「帝国」の絶頂期がまさにジョブズの末期(まつご)と重なることが手に取るようにわかる。
■「ナンバー2」を後継者に選出することの是非
著者自身のテーマであり、読者もまた多大な関心をもつであろう、事業継承のプロセスそのものは興味深い。だが正直いって、スティーブ・ジョブズ死後の記述を読んでもまったくワクワクしないのだ。すでにさまざまなIT関連の記事で読んで知っている事項だからということもあるが、ジョブズの後継者となったティム・クック氏のキャラクターにもその原因があるのだろう。
サプライチェーンの構築と運用を主たる業務としてきた後継者のクックは、厳密に数字で物事を捉え、理路整然と完璧な仕事をこなす能吏タイプで、ビジョナリータイプのジョブズとは真逆のタイプの人である。だが、そうだからこそ、ジョブズを支える「ナンバー2」の副官としては理想的な組み合わせであったわけだ。
ジョブズみずからが後継者として指名したことの意味は大きい。事業継承にかかわる混乱を未然に防ぐためであったが、なによりも事業に精通し、しかもジョブズという突出したキャラクターの持ち主であるカリスマ経営者を支えてきた人材であったためだ。
本書は、この後継者選出の是非について考える恰好の素材を提供してくれている。
■後継者への「移行期」の課題
本書には、経営者交代時の課題と試練が綿密な取材にもとづいて描かれている。移行期というものはもっとも難しい時期である。この時期の対応に失敗すると、企業経営に限らず組織というものはうまくいかなくなる可能性が高い。
移行期の課題とは、連続性と変化にかかわるものだ。経営の連続性を維持しつつ、かつ経営者交代にともない独自色を打ち出さなくてはならないという相互に矛盾する二律背反的な状況にあることだ。「変わらないためには、変わらなくてはならない」という表現をつかってもいいだろう。何世代にもわたってつづいてきた老舗(しにせ)には可能でも、一代で築き上げた企業には難しい課題である。
クックの場合は、一癖も二癖もある幹部連中をどうまとめていくかがまず大きな課題であった。ジョブズのような際だったカリスマ的なリーダーなら可能だったことも、能吏タイプの後継者には難しい課題だ。「神格化」の進行する死せるカリスマ創業者の存在を意識の外においやることはできないからだ。
目を外に向ければ、ライバル企業はいまだ創業経営者が最前線で君臨している。アマゾンしかり、グーグルしかり、フェイスブックしかり。これらに対し、かつてPC時代のライバルであったマイクロソフトも、スマホ時代のサムスンもまた、カリスマ創業者が去ったあとは迷走をつづけている。
■「破壊的イノベーション」は企業規模が拡大して「追われる立場」になると難しい
イノベーションを原動力としてきたアップルにとって、なによりも困難なことは、画期的なイノベーションを継続していくことだ。規模が拡大して「帝国」となった現在は、きわめて難しい。
独特の美学にもとづき、完璧な製品を市場に投入してきたアップルだが、試作品をつくって使用者からのフィードバックをもとに試行錯誤を経ながら完成品をつくりあげていくグーグルやフェイスブックのようなソフトウェア系企業との違いは大きい。後者のやり方が、イノベーション創出の主流となりつつあるだけに、なおさらのことだろう。
ジョブズ亡き後のアップルにとって、後継者のクック自身が全面的に関与していたサプライチェーンから綻びが始まってきたのは痛いところだろう。ファブレスメーカーとして自前の製造機能をもたないアップルは、委託生産先で発生しつづける問題への対処に追われている。
すでにベンチャーの規模ではない、企業価値ではエクソン・モービルを抜いて世界最大になったアップルである。株式を上場している以上、市場関係者は数字でしかものをみないし、それに応えるために企業自身も数字として成果を出し続けて行かなくてはならない。そのような状況で、失敗がつきものの画期的なイノベーションを生み出すことがいかに困難な課題であることか。
ジョブズ自身も愛読して実践してきたクリステンセン教授の『イノベーションのジレンマ』の教訓は、ジョブズ死後のアップルもまた「イノベーションのジレンマ」に陥ったケースとして記録されることになるのだろう。「追う立場」から「追われる立場」に変化しているのだ。「破壊的イノベーション」は企業規模が拡大して「追われる立場」になるときわめて難しい。これはソニーについても同様だ。
グーグルのアンドロイトが「オープンソース型」であるのに対し、アップルは「囲い込み型」のビジネスモデルで収益を上げてきたが。「破壊的イノーベション」による製品では大きな収益をもたらすこのビジネスモデルも、コモディティ化した製品ではかえって足かせになることも著者は示唆している。わたしはこの見解に同感だ。かつて松下電器(・・現在のパナソニック)に高収益をもたらした系列家電販売店チェーンによる販売モデルが、量販店時代に足かせになったことを想起させる。
守りに入った「帝国」はすぐに沈没することも崩壊することはないが、徐々に衰退していくものだ。日本語には盛者必衰という四文字熟語がある。アップルもまたその例外ではないということだろうか。
それにつけても、スティーブ・ジョブズという人が、いかに突出した例外的な存在であったことかが逆説的にあぶり出されるのである。カリスマ経営者に依存した企業は、急成長をとげても、つねに「カリスマリスク」がつきまとう。このことが「ジョブズ後のアップル」の推移を見ていくと、あらためて実感されるのである。
永続的な存在としてサステイナブルな企業とするためには、いたづらに規模を拡大するべきではないという教訓も引き出すことができるかもしれない。だが、いまだ進行中の事象であるだけに、時間がたってから振り返って検証してみるべきケ-ススタディといった内容である。本書の「その後」をぜひ読んでみたい。
PS この書評は R+(=レビュープラス)さまからの献本をいただいて執筆したものです。
PS2 この書評をブログにアップした2015年2月24日がジョブズの誕生日だったとはまったく知らなかった。56歳で亡くなったジョブズは生きていれば、今年はなんと60歳の還暦。なんという偶然の一致というべきか、それとも・・・。あらためてご冥福を祈ります。合掌 (2015年2月25日 記す)。
目 次
著者まえがき
序章 かつて私は世界を統べていた
第1章 去りゆくビジョナリー
第2章 ジョブズの現実歪曲
第3章 CEOは僕だ
第4章 在庫のアッティラ王
第5章 皇帝の死
第6章 ジョブズの影と黒子のクック
第7章 中国の将軍と労働者
第8章 アップルの猛獣使い
第9章 Siriの失敗
第10章 アンドロイドに水素爆弾を
第11章 イノベーションのジレンマ
第12章 工員の幻想と現実
第13章 ファイト・クラブ
第14章 きしむ社内、生まれないイノベーション
第15章 サプライヤーの反乱
第16章 果てしなく続く法廷闘争
第17章 臨界に達する
第18章 米国内で高まる批判
第19章 アップルストーリーのほころび
第20章 すりきれていくマニフェスト
終章2013年11月
謝辞
訳者あとがき
解説
原注
著者プロフィール
ケイン岩谷ゆかり(Yukari Iwatani Kane)
ジャーナリスト。1974年、東京生まれ。ジョージタウン大学外交学部(School of Foreign Service)卒業。父の仕事の関係で3歳の時に渡米、シカゴ、ニュージャージー州で子ども時代を過ごす。10歳で東京に戻ったものの、15歳で再び家族とメリーランド州へ。大学3年の時に1年間上智大学へ逆留学したが、その後アメリカへ再び戻る。アメリカのニュースマガジン、U.S. News and World Reportを経て、ロイターのワシントン支局、サンフランシスコ支局、シカゴ支局で勤務後、2003年末に特派員として東京支局に配属。通信業界、ゲーム業界などを担当。2006年にウォール・ストリート・ジャーナルへ転職。東京特派員としてテクノロジー業界を担当。2008年にサンフランシスコに配属、アップル社担当として活躍。スティーブ・ジョブズの肝臓移植など数々のスクープを出したのち、本書執筆のために退職。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。
訳者プロフィール
井口耕二(いぐち・こうじ)
1959年生まれ。東京大学工学部卒、米国オハイオ州立大学大学院修士課程修了。大手石油会社勤務を経て、1998年に技術・実務翻訳者として独立。翻訳活動のかたわら、プロ翻訳者の情報交換サイト、翻訳フォーラムを友人と共同で主宰するなど多方面で活躍している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。
解説者プロフィール
外村仁(ほかむら・ひとし)
戦略コンサルティング会社のベイン・アンド・カンパニーを経て、アップル社でマーケティングを担当。ジョン・スカリーからスティーブ・ジョブズまで5年間で4人のCEOに仕える。スイスIMDでMBAを取得後、シリコンバレーで起業、ストリーミング技術の会社を立ち上げ、売却。ファーストコンパスグループ共同代表、スタートアップ数社のアドバイザーやOpen Network Labの起業家アドバイザーなどのほか、エバーノート日本法人の会長も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)。
<関連サイト>
Appleのティム・クックCEO、ケイン・岩谷ゆかり氏の著書を「ナンセンス」と酷評 (2014年3月9日)
Yukari Iwatani Kane (元ウォールストリート・ジャーナルのアップル担当記者ケイン・岩谷ゆかり氏のサイト)
●アップルは「沈みゆく帝国」なのか(ケイン岩谷ゆかり)
第1回 皇帝亡きあとの帝国 ジョブズの亡霊と比べられるティム・クックCEO (ケイン岩谷ゆかり、日経ビジネスオンライン、2014年6月18日)
第2回 ジョブズの遺産、アップル・ユニバーシティ 幹部を鍛える研修プログラム (ケイン岩谷ゆかり、日経ビジネスオンライン、2014年6月25日)
第3回 広告から透けるアップルに欠けているもの シンク・ディファレント誕生と今の違い (ケイン岩谷ゆかり、日経ビジネスオンライン、2014年7月2日)
第4回 ジョブズが後継に選んだ男、ティム・クックは何者か? 故郷、アラバマ州ロバーツデールを訪ねる (ケイン岩谷ゆかり、日経ビジネスオンライン、2014年7月9日)
第5回 ジョブズが認めたデザイナー、ジョナサン・アイブ 天才は日立、ゼブラ製品もデザインしていた (ケイン岩谷ゆかり、日経ビジネスオンライン、2014年7月17日)
ジョブズ存命でも、アップルの進化難しかった 『沈みゆく帝国』著者、ケイン岩谷氏に聞く(前編) (東洋経済オンライン、2014年8月9日)
クック体制でアップルの均衡崩れつつある 『沈みゆく帝国』著者、ケイン岩谷氏に聞く(後編) (東洋経済オンライン、2014年8月11日)
アップル社(米国本社)の公式サイト
Steve Jobs Stanford Commencement Speech 2005 (スタンフォード大学での卒業祝辞スピーチ動画 英語・字幕なし)。
スピーチの英語原文はスタンフォード大学オフィシャルサイトに掲載。
・・ジョブズ氏の死生観も語られている
<ブログ内関連記事>
■アップル社
書評 『アップル帝国の正体』(五島直義・森川潤、文藝春秋社、2013)-アップルがつくりあげた最強のビジネスモデルの光と影を「末端」である日本から解明
・・まさにこのサプライチェーンのかかわる側面こそ、CEO職をジョブズから引き継いだかつてのナンバー2ティム・クックの業務であった
■スティーブ・ジョブズ関連
巨星墜つ-アップル社のスティーブ・ジョブズ会長が死去 享年56歳 (1955 - 2011)
スティーブ・ジョブズはすでに「偉人伝」の人になっていた!-日本の「学習まんが」の世界はじつに奥が深い
スティーブ・ジョブズの「読書リスト」-ジョブズの「引き出し」の中身をのぞいてみよう!
■カリスマ経営者退任後の経営
カリスマが去ったあとの後継者はイノベーティブな組織風土を維持できるか?-アップル社のスティーブ・ジョブズが経営の第一線から引退
「世襲」という 「事業承継」 はけっして容易ではない-それは「権力」をめぐる「覚悟」と「納得」と「信頼」の問題だ!
■ナンバー2という副官のあり方
書評 『No.2理論-最も大切な成功法則-』(西田文郎、現代書林、2012)-「ナンバー2」がなぜ発展期の企業には必要か?
・・ナンバー1とは根本的に異なる機能を果たすナンバー2の難しさ
最高の「ナンバー2」とは?-もう一人のホンダ創業者・藤沢武夫に学ぶ
・・創業経営者の藤沢武夫は本田宗一郎とともに退任した
「長靴をはいた猫」 は 「ナンバー2」なのだった!-シャルル・ペローの 「大人の童話」 の一つの読み方
・・優秀なナンバー2がいかに重要であるか!
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
end